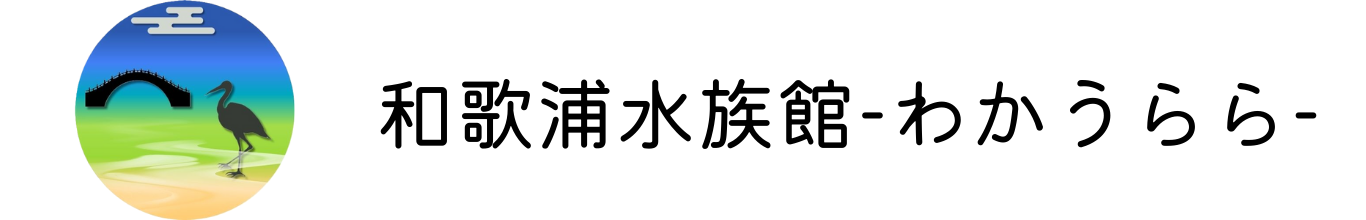
このページでは、 トップページのポスターや「水族館について」で述べた“日本の海”とはどのようなものか、 水族館の現状を交えながら解説していきます!
皆さんは「日本の海」といえば、何をイメージしますか?
恐らくほとんどの人は、これを思い浮かべたことでしょう!
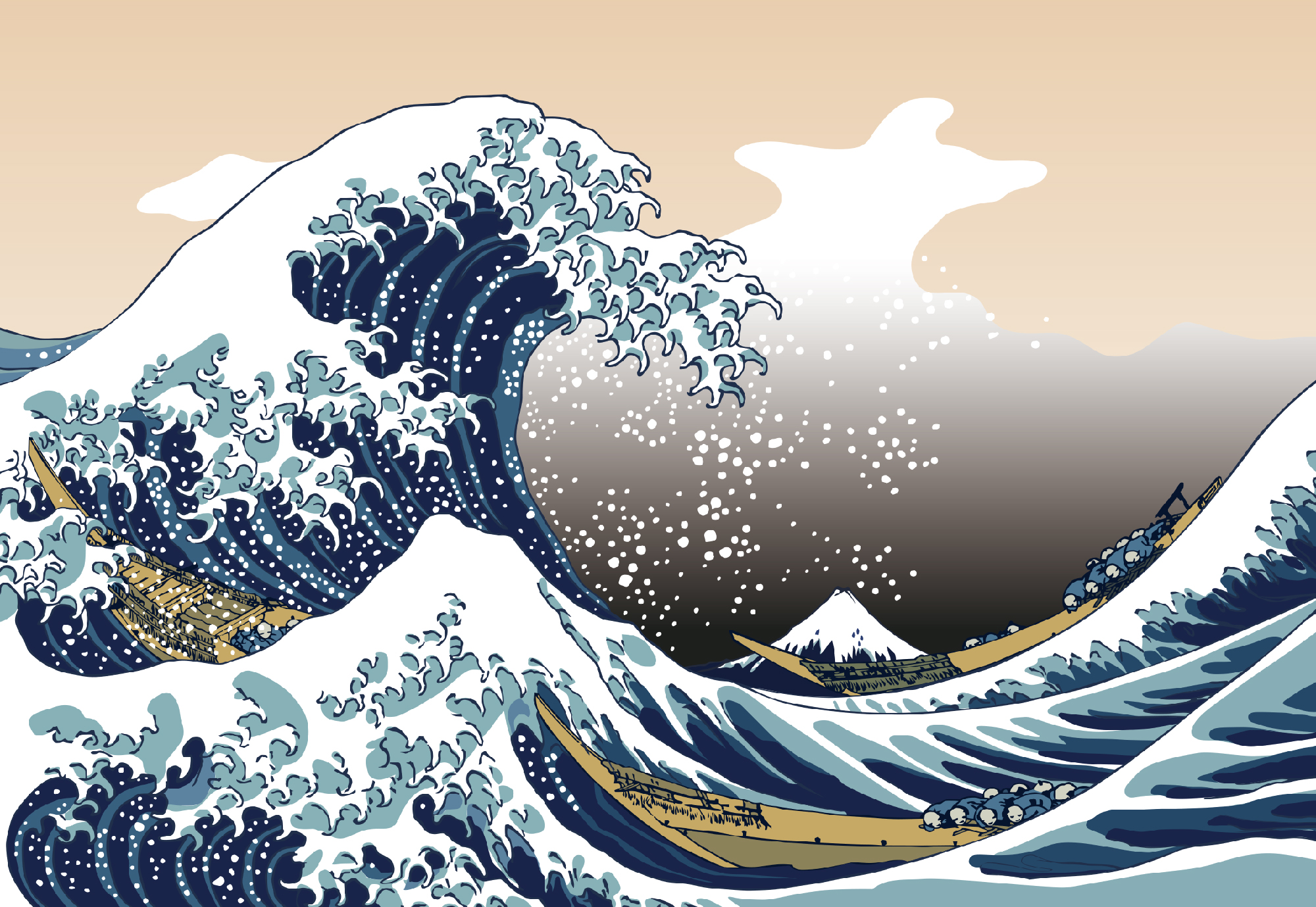
そう、葛飾北斎の神奈川沖浪裏です。
まさに日本が世界に誇る代表的な海のイメージですよね~
では次に、水族館と言えば、どんなイメージですか?
恐らくそこには、和の要素はほとんどないと思います。
可愛くて、大きくて、ワクワクして、ドキドキして、映え~ですよね。
こんな感じとか

こんな感じですよね~

そう、実は私たちは無意識のうちに、
「日本の海」というイメージと「水族館」のイメージが全く別モノと認識しているのかもしれません!
その理由は、水族館で日本らしい空間があまり整備されてこなかったからでしょう
葛飾北斎のおかげで、世界中に「日本の海と言えばこの絵!」というイメージが定着しているにも関わらず、 水族館大国である日本で「日本らしい空間」が整備されていないのは 日本が持つポテンシャルを、まだまだ発揮できていないと言えるでしょう!
他にも、今の日本国内の水族館のほとんどは生物学的な展示で、 そこから環境問題を訴えていることが圧倒的に多いというのも、非常に勿体ないと言えるでしょう。
どういう意味か、簡単に言うと、 この生き物はどんな場所に暮らして、どんな体の特徴があって、どんな変わった特技があるのか、 などといった紹介文を踏まえて、海洋汚染や自然破壊といった 現在の環境問題のことを伝えている水族館の展示、見たことないですか?
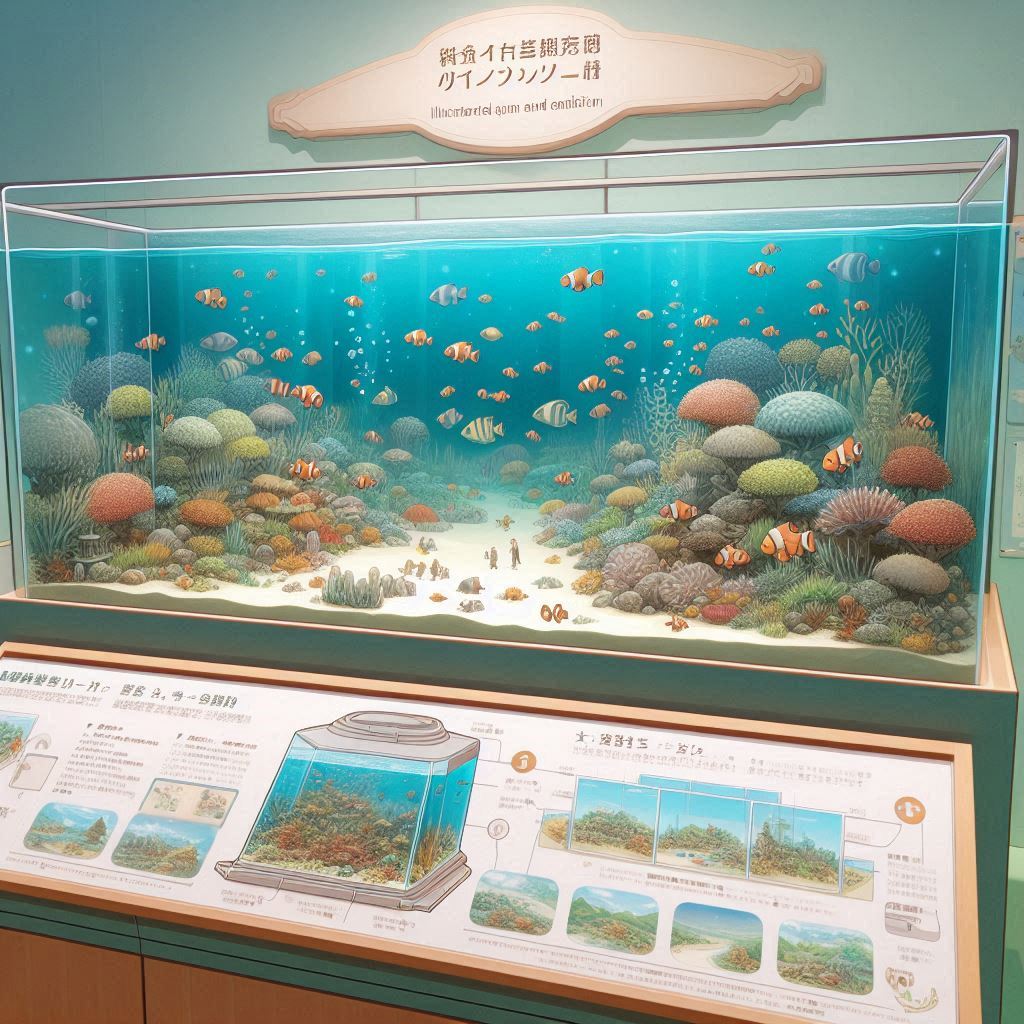
生成AIで作成したイメージ
要は、これだと非常に勿体ない、という訳です。
もちろん、近年はSDGsに対する関心も高まっていることもあるので、 生物学的な視点から環境問題を訴えるのは、間違いなく必要なことだとは思います。 しかし、日本人と海の関係性を考えれば、もう少し情報が必要だと思います。

単に保護すべき存在、環境を守ろう!だけでは、 他人事と捉えてしまう人がほとんどだと思います。 何故なら、親近感を感じづらいからです。 この生き物たちは、どのように日本人と関わってきたのか、 そんな日常生活と関わってきた情報を加えるだけで、 人との関わりを理解しやすくなるのではないでしょうか。 例えばですが、
などといった紹介文にすると、先ほどよりも少し身近な存在に感じませんか? そう、これまでの水族館で伝えていた情報に、歴史・文化的な情報を加えることで、 身近な存在として認知しやすくなるんです!
日本人は古くから魚を食べ、海の景観を愛し、船で多くの交易を行ってきました。 他にも『万葉集』にも魚は登場していますし、 『浦島太郎』をはじめとする多くのおとぎ話の舞台としても海は重要な存在でした。 江戸時代には伊藤若冲などが描いた魚の絵も人気を呼び、 全国各地では魚類研究が盛んになり、多くの魚図鑑も作成されていました。 そして何より、世界有数の豊富さを誇る魚料理も無視できないでしょう。

そんな歴史・文化の関わりを従来のキラキラした水族館で伝えようとすると、 展示パネルの文章だけになってしまい、伝えづらいことに変わりありません。 そこで、水族館のデザインごと歴史・文化をベースにした和風空間にすることで、 人と生物・自然環境との関わりを生物学、歴史学の双方から発信しやすい空間となるので、 より身近な世界の話として来館者に届けることが出来るのではないでしょうか。

生物学的な情報と、環境問題だけでなく、歴史・文化に関する情報を加えて発信することで、 「日本人は海とこのように関わってきましたが、現状は多くの環境問題が発生しているので、豊かな環境を守っていこう!」 という流れが生まれ、従来よりも説得力が増すと考えられます。