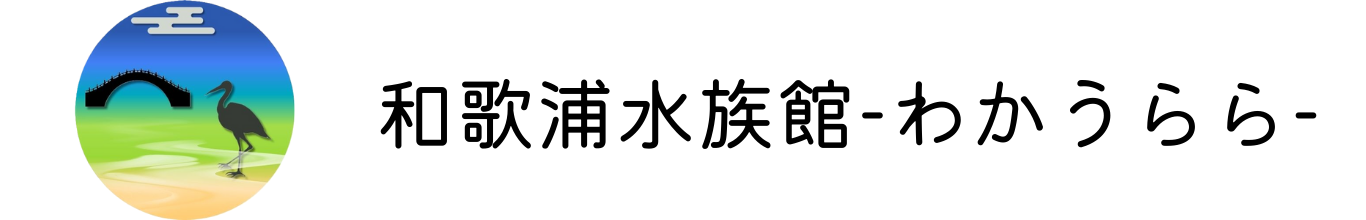
このページでは、この水族館のコンセプトと そのコンセプトにした理由を、 水族館の現状を交えて解説していきます!
和歌山に水族館を整備するなら、そのコンセプトは、
日本の海、
日本の水、
そして文化
が最も適していると思われます。
そもそも日本は、世界中にある水族館のうち、1/5が日本にあると言われるほどの水族館大国です。
その歴史を簡単に振り返ると、
| 年号/およその年代 | 出来事 |
|---|---|
| 1882年 | 日本初の水族館「うをのぞき」が東京上野動物園の敷地内にオープン |
| 1915年 | 上野動物園でペンギンの飼育が始まり、日本中にペンギン飼育が広がる
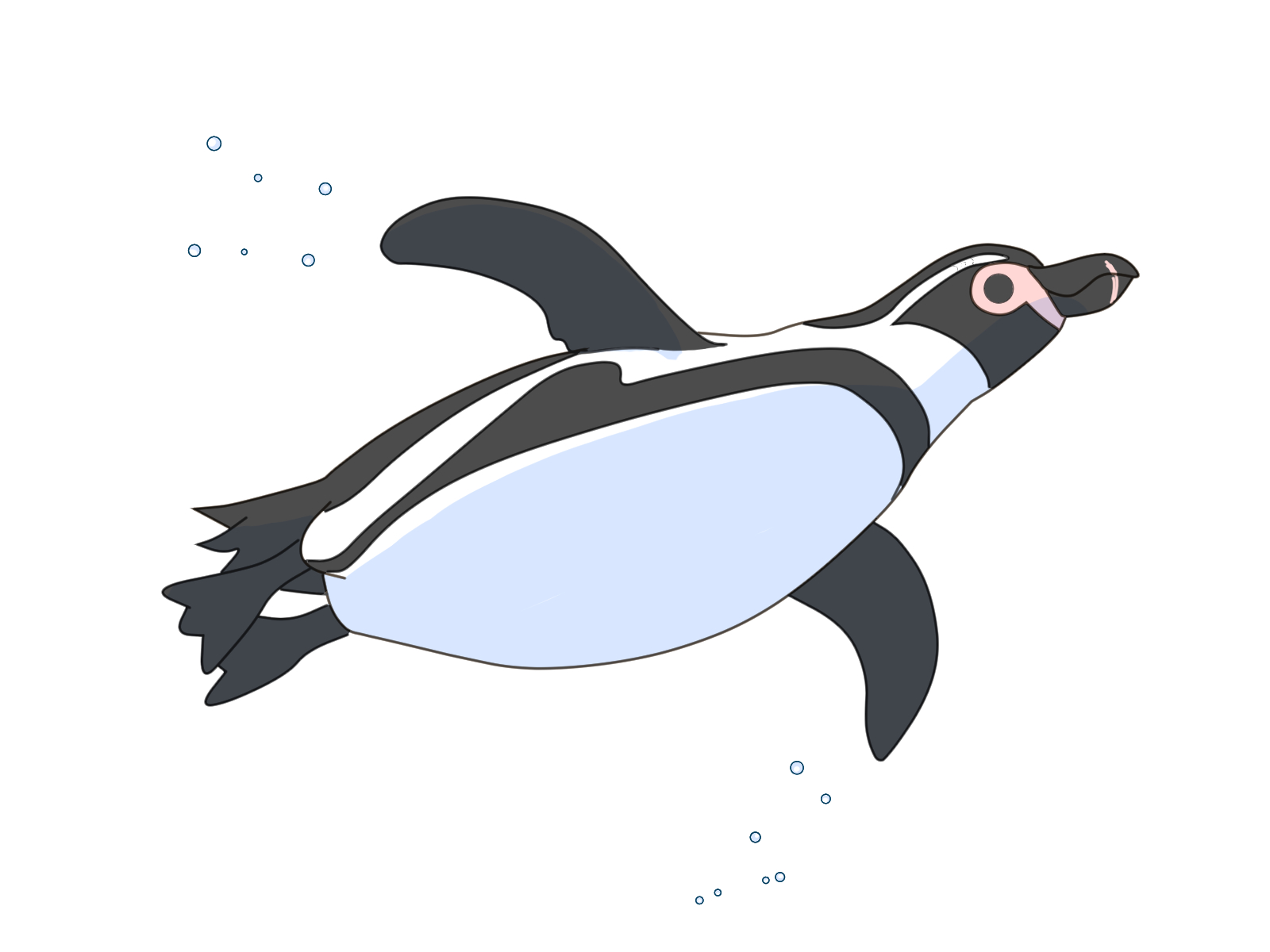
|
| 1957年 | 江ノ島水族館(現・新江ノ島水族館)で日本初のイルカショーが始まる
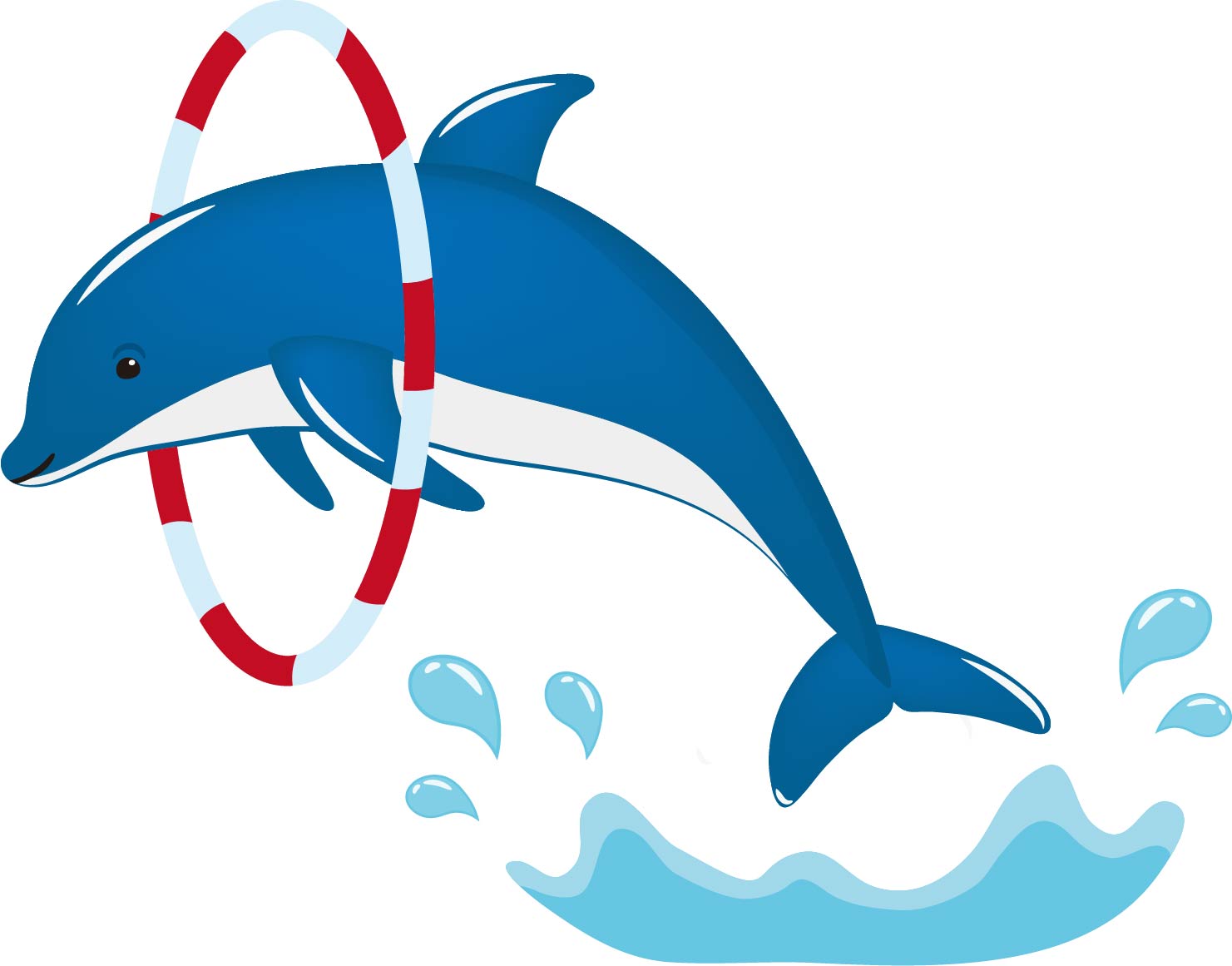
|
| 1990年代 | バブル時代の水族館ブーム(八景島シーパラダイス、名古屋港水族館南館、海遊館、マリンワールド海の中道など) |
ラッコの飼育ブーム

|
|
| 2000年代 | 大型水族館の成熟期(名古屋港水族館北館、沖縄美ら海水族館など) |
| 旭山動物園にはじまる行動展示ブーム | |
| 2010年代 | 地域振興の起爆剤として利用され始める(むろと廃校水族館など) |
山形県の加茂水族館にはじまるクラゲブーム
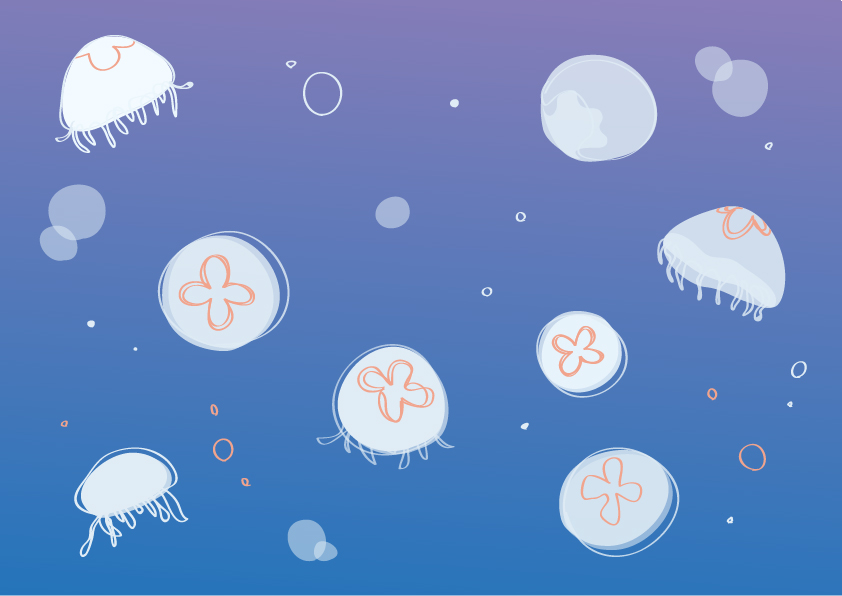
|
|
| 2010年代後半~ | おしゃれな空間、映える空間が意識されるように(NIFREL、atoa、四国水族館、DMMかりゆし水族館など) |
戦前から観光スポットとして扱われていた水族館は、 今では日本人の休日に欠かせない施設となっています!
では今後、どんな水族館を整備すればいいのかという話になります。 ひと昔前ならば、世界最大の水槽などを整備することで集客が成功する時代だったと思います。 しかし、現在の日本では世界最大の水族館を整備することは、まず不可能です。 なぜかというと、日本以外での水族館の規模が大き過ぎるからです。
例えば、2012年に開館したシンガポールのシーアクアリウムの大水槽は、 日本一大きい水族館の1つである美ら海水族館の大水槽の2倍以上の規模で、 同じく2014年に開館した中国の珠海長陵海洋王国の大水槽に至っては、 美ら海水族館の約4倍の規模となっています。 水槽以外でも、2023年に開館したUAEのシーワールド・アブダビの体積は美ら海水族館や海遊館のおよそ6倍にもなります。 北米有数の人気を誇る、アメリカのジョージア水族館でも美ら海水族館や海遊館の2倍の規模を誇っています。 今の日本では経済的にも敷地面積的にもこれらの水族館に匹敵するものを建設するのは不可能です。
シンガポール/シーアクアリウムの館内の様子は以下の動画をどうぞ
中国/珠海長陵海洋王国の館内の様子は以下の動画からどうぞ
UAE/シーワールド・アブダビの館内の様子は以下の動画からどうぞ
アメリカ/ジョージア水族館の館内の様子は以下の動画からどうぞ
これらの動画を見てもらうと、とても日本ではこれらに匹敵する水族館を建設できないとわかると思います。 また、日本最大という言葉も、もはや現在では集客力が見込める言葉ではないように思われます。 ましてや、 近年よく見かけるような、おしゃれな空間や映えを意識した水族館がこのまま増加してしまうと、 共倒れの危険性が高まるばかりでしょう。
つまり、これからは規模ではなく、差別化を図れるような中身で勝負しなければならない時代が来るということです。
そんな中で、このサイトの作成者・キラクが提案するのが、「日本らしさ」です。
他の地域では真似できない、日本だからこそ建設できる空間ならば、
規模の大きい水族館とも勝負できると考えられます。
そう、和歌浦水族館のメインテーマに掲げるのは、「日本」です!

生成AIで作成したイメージ①
こんな感じとか、

生成AIで作成したイメージ②
こんな感じのイメージで
これまでの水族館ではあまり見かけてこなかった「日本」らしい内装で、 日本人と海、そして川などの水はどのように関わってきたのか、 そしてそこからどんな文化が生まれたのか、 という日本人との繋がりをコンセプトにした水族館です!